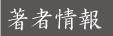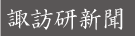先日小倉で開かれた人工知能全国大会に出席したとき、日立の研究所時代の上司とお会いした。「諏訪くん、人工知能学会も随分雰囲気が変わっちゃったね」、「そうですね、フレーム問題を忘れてしまったひとが多いのですかね?」。このちょっとした会話に、ここ10年ほど感じてきた想いが凝縮していた。
人工知能は第三次ブームを迎えている。ディープラーニング(深層学習)という学習アルゴリズムが開発され、「ネットに転がるビッグデータから自動的に概念が学習される時代になった」、「コンピュータは、ひとには捌き切れないビッグデータに潜むパターンを見出して賢くなる」、「様々な社会応用が想定され、コンピュータに置き換わる仕事がたくさんあるはず」など、大賑わいである。
第二次ブームは、僕が学生の頃だった。専門家が有する専門知識をコンピュータに入れ込めば、コンピュータも賢くなる!と社会が期待を持った。俗に言うエキスパートシステムである。しかしすぐに、その限界が露になった。知識を詰め込めば詰め込むほど問題空間は大きくなり、(知識適用における)空間探索に時間がかかる。ひとは全数探索などせず、空間をばっさり枝刈りして探索空間を狭める。一方、コンピュータは、空間を狭める方策が記述されない限り、枝刈りはできない。
より一般的に言い換えれば、ひとは考える枠(「フレーム」と称する)を柔軟に変更できるということだ。枝刈りは枠を狭くする方向である。必要とあらば、いきなり枠を広げることもする。お笑いはその典型であろう。ツッコミとボケからなる漫才を例にとろう。ボケ担当の芸人は考える枠を常識的な範囲から拡大し、凡人には思いも寄らない領域に言及する。「そこ(に飛びますか)?!!」。売れている芸人たちの飛び方に、まざまざと豊かな発想力を見せられる。凡人にはその飛び方は思いつかないが、提示されると「あ〜、それもありだし、ユニークだな」と納得し、感心する。そこが芸人の凄いところである。
エキスパートシステムは各専門領域を定義し、領域に閉じた知識を記述してコンピュータに入れ込んだ。しかし、ひとの日常生活は、領域が明確に分割されているわけではない。個々の領域は存在するがその境界は明確ではなく、連続的につながっていたりする。剣道家は、剣道の間合いのスキルを考えていたとしても、やがて、立つこと、呼吸すること、姿勢のあり方に思考が及び、「・・ということは、普段の生活の話じゃん」と気づく。剣道のスキルは、例えば腹の底から声を出すこと、説得力をもつ語りをすること、踏ん切ることに関係するかもしれない。つまり剣道も生活のなかにある[1]。
緩やかに連続性のある概念世界をひとは柔軟に行き来するのだ。ボケる芸人はその体現のしかたで世間をあっといわせる開拓者である。いまの人工知能にはそれができないことを指して、「フレーム問題」と称する。哲学的な問いでもある。この問題への気づきが、第二次ブームの火が消えた最大の原因であった。
コンピュータの処理速度は、当時とは比べられないほど速くなった。インターネットの普及、情報処理技術の発展によって、一般市民が生活にまつわるデータを自由にアップできる。産業界も社会・経済活動に関するデータを生成・集積・活用できる。多岐にわたるビッグデータの環境が整ったのである。そして、ビッグデータに埋もれる共通パターンを発見するアルゴリズムが開発された。
しかしちょっと待った!
フレーム問題は30年間手つかずのまま未解決である。実は、ひとも決してフレーム問題を解決しているわけではない[2]のだが、(擬似的に)解決し、うまくやってのけている。ただし、どう「うまく」やっているのかをわれわれは知らない。
人工知能研究には二つのタイプの研究がある。そもそもひとの知はどのようなメカニズムで機能するのかを探る、いわゆる生身のひとの研究。そして、賢く振る舞う/行動をするコンピュータを(人工的に)つくる研究。二つは車の両輪のようなものである。前者の知見が後者にフィードされる。そして、知的なコンピュータを動かしてみたときに実世界で起こる様々な相互作用から、ひとの知と比べて劣る・異なる・優れていることを挙げ、前者の研究にフィードする。いわゆる構成的[3]といわれるパラダイムである。
冒頭に紹介した会話にあるのは、前者の研究を担う研究者が減ったという想いである。産業的・社会的に役に立つ、すぐ金になる研究に飛びつき、研究開発に邁進する。前者の研究の重要性を説かれると、「でも、人と同じメカニズムで賢くならなくてもよい」と答え、前者の研究を省みない。二つの研究の「構成的な循環」を忘れてしまったかのような風潮に、僕もかつての上司も危惧の念を抱いているのだ。長年続いた不景気がそういう研究風土を生んでしまったならば、是正しなければならない。いつの時代も基礎研究の芽は摘むべきではない。
AI小説の試みが耳目を集めているが、それには二つの研究を構成的に循環させる意図が感じられる。公立はこだて未来大学の松原さん曰く、「いまはひとがテーマや粗筋の大方(約八割)を担っていて、残りの二割をコンピュータがやっている」。フレーム問題が関わる発想の部分はまだひとがやっていることを、そして現状ではこの比率であることをしかと認識し、ひとの発想のメカニズムについて、前者の研究を進める努力が学界全体に求められるのではないか。わたしは、臨機応変さとは何か、ボケるってどういう知かを、身体性の観点から探究したいと考えている。
参考文献
[1] 諏訪正樹, 赤石智哉. (2010)身体スキル探究というデザインの術. 認知科学, Vol.17,No.3,pp.417-429.
[2] 松原仁, 橋田浩一. (1989)情報の部分性とフレーム問題の解決不能性. 人工知能学会誌, Vol.4,No.6,pp.695-703.
[3] 諏訪正樹, 藤井晴行. (2015)知のデザイン 自分ごととして考えよう. 近代科学社.
(諏訪研新聞 平成28年7月15日付)