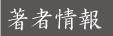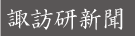先日デザイン学会があって、パネルディスカッション登壇の任を果たした。パネル討論の企画者の意図は、デザインという営為が、「つくる人」と「使う人」に分かれていてよいのか? 現在のデザイン研究って現在ある形でよいのか? というものだった。普段デザイン業界にいない僕がこの場に呼ばれて喋る。何を期待されているかを考えたときに、デザイン研究というフィールドを外から見て吠えてほしい。そういう意図を感じた。
デザイン研究というフィールドにいる研究者は、「いわゆるデザイナー」が多い。そんな人々が集まる場で僕が偉そうなことを言ってよいのかと躊躇する気持ちもないわけではなかった。でも、一つ、常々感じてきたことを今こそ言ってしまおうという誘惑には勝てず、ガツンと喋ることにした。
それは、「デザイン」という言葉が狭すぎるのではないかということである。いわゆるデザインを生業にする人たちがやっていることが「デザイン」であると、デザイン研究者の多くも、世の中も考えている。その通念に僕は待ったをかけたいのだ。
ちなみに、僕はいわゆる職業デザイナーではないが、自分が一生懸命生きることをデザインしているが、それは社会通念的には「デザイン行為」とはみなされない。
さらに言えば、(僕がやっている学問は認知科学であるが)認知科学とは、生活からかけ離れた実験室という環境の中で人の性質を調べ上げる学問ではなく、世界を見る視点を養い、自分が属する社会やコミュニティーをデザインし、そこでの生を全うすることをデザインする実践的な学問だと思うのである。
綺麗なプロダクト、便利なツール、そして社会的に役に立つと思われるものごとをつくりだすことだけがデザインではない。もちろんそういうものごとをつくりだすことは、デザインの重要な一側面ではある。しかし、そこに欠けているのは、「問う」ということではないかと思うのである。
私の「デザイン」の定義は、「実践する」こと(やってみること、つくりだすことも含む)と「問う」ことのサイクルである。問うとは、違和感を抱く、感触を得る、疑問を抱く、問題点を見出す、分析する、仮説を立てる、目標を立てるなどの行為の総称である。本人も明確に論理的に語れない曖昧な行為から、明確に言葉化できる行為まで、その順番に並べてある。
問うからこそ、何をつくりだすべきかについてアイディアが浮かび、そのアイディアを実践する(つくりだす)からこそ、また問いが生まれる。デザインのサイクルに終わりはない。
デザインをこのように捉えるとき、現在のいわゆるデザイン研究に僕は一抹の物足らなさを感じる。理由は二つある。第一に、便利で役に立つ(とデザイナーが思う)機能をつくりだすことに終始して、問うことと実践することのサイクルが回っていないと思うのだ。問うことには「分析すること」も含まれる。デザイナーがつくりだしたものごとが、ユーザーの生活を、もしくは生活感性をどう変えたか? そんな分析評価に地道に時間を費やす研究は本当に少ない。つまり、デザイン研究の多くが、サイクルが回っているとは言い難い。過去の新聞記事(第10回)でも書いたが、「認知実験」という名前が安易すぎる。ちょこっとユーザーを集めてインタビューをしたり、アンケートに答えてもらったりするだけでは、ユーザーの生活や生活感性をどう変えたかなど、わかりようがない[1]。
さらに言えば、「分析する」だけでは、十全なる問いとは言えない。先にリストアップしたように、問うことは、違和感を抱く、感触を得る、疑問を抱くなどの曖昧模糊な行為も含んでいる。パキッと明確に語ることができるようになる前に、人の認知にはこういう曖昧模糊な状態が芽生えている。問いはそこから始まる。それを経て次第に意識が明確になり、明確に問題点を意識したり、分析したり、仮説を立てたりすることができるようになる。
デザイン研究は、そういった曖昧模糊な状態をも題材にすべきではないか? 新しくつくりだしたものごとが生活や生活意識をどう変えたかを調べる認知実験は、人が生きる中でそのように曖昧に悩んでいる状態をもデータとして取得すべきであると思うのだ。
そう考えたとき、デザイン研究に対する第二の物足らなさが浮かび上がってくる。「デザイン」として研究の対象になっているものごとが、狭義すぎやしないか?と思う。社会的に役に立つものごとをつくりだすだけではなく、是非、人が社会の中で生を営むこと、つまり「生きること」を研究対象にして欲しい。生きることは、やってみることを問うことの連続である。つまり生きることはデザインそのものなのだ。であるとするならば、研究者自身が一生懸命生きている生き様そのものを研究対象にすることは、デザイン研究の「ど真ん中」であるはずだ。
別の言い方をすると、デザイナー自らの、もしくは人の知を研究対象としている心理学者や認知科学者自らの「一人称研究」[2]ということになる。自分が社会の中で一生懸命生きている様を、一人称の視点から(「現象学の考え方を基本理念にして」と言い換えてもよい)見て記述し、そのデータをもとに自らの生き様を分析するとともに、生き様を構成的に変えていくタイプの研究である。
こういう意識がデザイン研究分野に芽生えたとしたら、従来の「うわべだけの認知実験」は当然影をひそめる。デザイン研究は、デザイナー(いわゆる職業デザイナーだけではなく、私のように自己の生を一生懸命デザインしている人も含め)が生きることを実践し、問い、そのサイクルを回す過程で新しいものごとを次々に世に生み出すものになるであろう。デザイン研究の分野に、そのムーブメントを盛り上げたいものである。
参考文献・URL
[1] 諏訪正樹:「自分ごととして考える」ことを促す認知実験のあり方, 建築討論WEB版, Vol.9(2016年7-9月号), (2016). http://touron.aij.or.jp/2016/09/2637
[2] 諏訪正樹, 堀浩一(編著), 伊藤毅志, 松原仁, 阿部明典, 大武美保子, 松尾豊, 藤井晴行, 中島秀之(著). (2015). 一人称研究のすすめ–知能研究の新しい潮流. 近代科学社.
(諏訪研新聞 平成29年10月24日付)