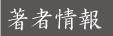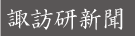「真実を追い求める」科学的態度
ひとの知を探究する学問が「真実をつかまえよう」という態度に縛られて、身動きが取れなくなっている。その態度を頑なに貫くのではなく、「語って醸成される意味を扱う」という態度も併せ持つことが肝要である。なんのこっちゃ?となっている方に解説を試みたい。
皆、子どもの頃から、「真実を追い求める」科学的態度を教育される。「科学」は、現象を、誰が見ても明白に存在する特徴の列挙と、その特徴同士の関係の実証によって、説明することを目指す。「誰から見ても明白に存在する」とは、客観性のことだ。それに対して、主観は人によって異なる。職業、性格や人生背景、抱いている思想や理念に応じて、同じ現象に遭遇しても、着眼する側面や解釈が異なる。
「科学」は客観性を重んじ、主観性を排除する。社会科で、街の大通りを昼時12時から1時間に通る車の台数を数える調査課題が出されたとしよう。数え間違いがないように、同じ地点に複数の生徒が立って数える。「156台」。まさに客観的なデータである。「格好いい車の台数は?」。質問が変わった途端、観察は客観的ではなくなる。「格好いい」は、主観的評価であり、科学的探究の対象にはならない。「真実を追い求める」態度の礎は、客観性である。
心のできごとの「真実」はつかめない
心を扱う心理学や認知科学にも、その態度を適用してよいのか?現在の心理学や認知科学は「科学」にならんとするがあまり、心の中で生じていること(思考や感情)についても「真実をつかまえる」態度で探究する傾向が強い。もともと、必ずしも「科学」を志向する学問ではなかったはずである(第16回の記事を参照のこと)。僕はそこに違和感を感じるのだ。
心で生じているものごとの「真実」は、果たしてつかめるのか?他者には決して掴めない。親しい間柄ならば推測は可能だ。しかし、「真実」と実証するための客観的な観察は不可能である。
では、本人はどうか?「難しい」としか言いようがない。心に去来したすべての思考内容や感情を、リアルタイムに記録/記憶することは叶わない。そんな心持ちになろうものなら、当の経験が疎かになる。つまり、生きることの邪魔になる。
リアルタイムな記録が生きることの邪魔になるからこそ、人は、(しょうがなく?)経験を振り返る。しかし、振り返りは、本質的に取捨選択的にならざるをえない。過去に去来した思考内容や感情のすべてに、等しくアクセスすることなどない。たまたま関心が及んだものごとだけが選ばれ、語られる。「真実をつかまえる」態度からは程遠い。結局のところ、心で生じたものごとの「真実」は、本人でさえつかみきれない。
人は、語って自己をつくる
人は語ることが好きである。心の世界については、本人でさえも「真実に辿り着けない」のが実情なのに、人は、なぜ、経験を振り返って語るのだろうか?語り続けていれば、いつかは真実に辿り着けると思っているのか?そうではないと僕は思う。
振り返って語るとき、必ず取捨選択がなされると先に書いたが、人は、自分が選んだものごとに、ある「意味」を見出す。逆の言い方をすれば、意味を見出せることだけを選択している。取捨選択と意味付けは、どちらが先でもない、常にセットなのだ。
「意味」とは何か?経験を物語り、そこに意味を見出すことによって、世界を見る新しい視点を手に入れることが可能になる。ひいては、生きる指針と潤いを得る。そのことを直感している(知っている)から、人は経験を振り返って語るのだ。日々の出来事を語った場合と、語らずに時が過ぎゆくままに任せた場合とでは、微妙にその後の人生が変わってくる。そういうターニングポイントが日常には偏在していて、知らず知らずのうちに、私たちは、人生の歩みを方向付けている。語ることで、自己がつくられる(更新される)。自己が変容すれば、語りたくなることも刷新される。
日々常に語るのがよいと、論じているのではない。語れないことも多々あるだろう。語るべきか否かと迷うこともなくも、ただ語らずに流していることの方が多いだろう。語れる時に大いに語ればよい。
ただし、語るべきかどうか迷ったら、なるべく、ちょっとでもいいから語ってみよう。(僕が提唱する「からだメタ認知」という学びの理論によれば)、自身の経験を語るというメタ認知行為は、それまで着眼したことのないポイントに気づくチャンスを提供し、生きるための指針を与えてくれるから。
意味の復権
学問的態度に話を戻そう。心の真実は誰にもつかむことができないのなら、認知科学や心理学は、「語ることによって醸成される意味」を扱うことにシフトするのがよい。更に言えば、(こちらの方がより強い理由なのだが)、生きる上で人が求めているのは「意味」であるからである。学問の使命は「生きることに資する」こと、新しい知見や仮説を世に提示するによって、より豊かに生きることを促すことである。したがって、ひとがよりよく生きることに資するためには、心を扱う学問は「意味の世界」を扱うべきだと思うのだ。民族心理学を提唱したジェローム・ブルナーの著書『意味の復権』もそのことを強く主張している。
植物状態の患者と「目が合う」
「真実」と「意味」の違いを如実に示す実践事例を最後に紹介したい。西村ユミ氏の『語りかける身体看護ケアの現象学』には、植物状態の患者にプライマリーナースとして向き合う看護師たちの苦悶が赤裸々に語られている。植物状態の患者は、医学上、たとえ目を開いていても意識はなく、他者とのコミュニケーションは単純なものさえ築けないとされている。しかし、プライマリーナースたちは、時に、患者さんと「目が合う」感覚を得ることがあるという。看護行為に対する反射的な反応とは何かが異なり、目が一瞬キラリと光る感覚があるらしい。他の看護師にはわからない、長期間看護を受け持つプライマリーならではの感覚だそうだ。
本当に「目が合った」のだろうか?プライマリーゆえの患者への思い入れに起因する錯覚だろうか?看護師たち自身も揺れ、迷う。迷いながら、そして、もっと良い看護はできないものかと悶絶しながら、看護師は経験を語り続ける。しかし、彼らの問いには答えが出ない。
僕は、本当に「目が合った」かどうかの「真実」よりも、看護師本人が「目が合ったかもしれない」と直感しているということの方が重要だと思うのだ。看護経験を語り、「目が合ったのかもしれない」と意味を見出す方が、(たとえ、それが真実かどうかわからないとしても)その後のより良い看護につながるからである。看護師としての「意味の醸成」が、看護師としてよりよく生きることにつながる。そういうエピソードだと僕は解釈している。
科学的探究とはなんであろうか?認知科学や心理学は、今、真剣に問うべきであろう。
参考文献
西村ユミ.(2018).語りかける身体看護ケアの現象学、講談社.
(諏訪研新聞 平成31年1月15日付)