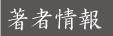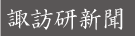「認知実験」のあり様に喝!
わたしはこれまで数多くの研究発表を拝聴してきましたが、ひとつだけ、どうしても許せない類いの研究があります。新しいものごと(例えば、新機能を備えた物や、新しい考え方に基づく教育プログラム)を提案したら、それがひとに(ユーザーに)どういう影響や効果を与えるかを調査するのが定番です。「認知実験」ということばが使われることもあります。許せないと思うこととは、認知実験を行う多くの研究で、影響や効果の測定/評価のしかたが片手間なことです。そんな片手間なやりかたで、影響や効果が評価できましたと胸を張らないでほしい! 片手間であることは本人も薄々わかっているのではありませんか? なんだかなあと残念でしかたないのです。
何が片手間だと思うのかを説明します。認知実験とは、より一般的に言うならば、ひとの意識のデータを採取する試みです。意識調査の手法として誰もが思いつくのは、アンケートやインタビューでしょう。アンケートでは、研究者が注目する項目(より専門的用語でいうならば「変数」)が列挙され、ユーザーは各項目について意見を求められます。インタビューには、構造化インタビュー、半構造化インタビューなど、研究者が用意したインタビュー項目がどれくらいかちっと決まっているかによって差異があります。認知実験という観点でいうならば、わたしは、アンケートもインタビューも全く不十分だと思います。なぜならば、両手法とも「その場限りの」意見を採取する手法であるからです。
認知実験は「生活実験」であれ!
暗黙知という概念があります。ひとは自分のからだがやっていること/感じていることを十分にはことばで語れないという概念です。新しく提案されたものごとの善し悪しを、果たして「その場限りで」ことばで表現できるのでしょうか?
構成的研究という概念もあります。公立はこだて未来大学の中島秀之さん、東京工業大学の藤井晴行さんとわたしは、かれこれ十年近く、FNSループという考え方[1][2]を提唱してきました。新しいものごとを世に提案すると、社会的なインタラクションを引き起こします。そのときの社会で生起しているものごとや人びとの意識・時代思想と相まって、世に提案してみる前には予想だにしなかったインタラクションが芽生え、提案されたものごとの新たな側面が見えてくるという概念です。「ある側面」に気づいたおかげで、次世代の新たなアイディアが湧くこともあります。良いことばかりとは限りません。思いも寄らぬ悪い使われ方をされ、そうであればそのものごとは廃止した方がよいねとなるやもしれません。
構成的という概念の肝は、「提案したり、外的に表象する(形として表す)ことによって社会的審判を受けるからこそ、新たな側面が顕在化(もしくは創造)される」という点です。社会的審判にはある一定の時間がかかるのです。
暗黙知や構成的研究という概念に照らして考えると、認知実験のあるべき姿も自ずと見えてきます。アンケートやインタビューを受けている「その場限りの」意見ではなく、「リアルな生活のなかで時間をかけて」ひとの意識を採取する必要があります。提案された新たなものごとが生活の行動や意識をどう変えるのか? 生活のなかでそれを使ってみたり、その考え方を実践してみたりするまでは、行動や意識に何が生じるかは誰にも(本人にさえも)わからないのです。
認知実験は「生活実験」であれ! わたしはそう叫びたいのです。例えば、新しいインターフェイスを提案するならば、まず研究者が自分を被験者にして、生活のなかで一定期間使ってみた結果を発表することがスタートではないでしょうか? 一人称研究[2]という、連載第9回記事で紹介した考え方です。
自分ごととして考えさせる意識調査
「生活実験」の肝は、被験者に、「自分ごととして考えさせる」ことであるという言い方もできます。わたしと藤井さんは最近『知のデザイン—自分ごととして考えよう』という書[3]を出版しました。詳細は書をお読みいただきたいのですが、簡単に言うならば、「自分ごととして考える」とは、自分のからだで実際に感じたものごとを基に考えること、自分の生活の実体や問題意識に照らして考えることです。「その場限りの」意識調査で、果たして被験者は、新しく提案されたものごとを自分ごととして捉え、自分に対する効果や影響を評価できるでしょうか? 答えは否です。片手間だと批判するのはそういう理由からです。
小学生の読書感想文を例にとりましょう。幼い子どもは、新しいものごと(読書でいえば、読んだ内容)に相対して、からだでは確実に何かを感受していたとしても、克明にことばで綴る技量を持ち合わせていません。感受する力もまだ磨かれていないかもしれません。からだで受け取ったことを少しずつことばで表現する訓練を積みながら、「楽しかったです」、「主人公は偉いと思いました」の域を脱し、意識表現の粒度や深さを培います。
「その場限りの」意識調査は、大人が相手なのに、小学生の読書感想文程度のことしか求めていないように思います。生活のなかで試して初めて芽生える意識を取得しようとしてこそ、「自分ごととして考えさせる」意識調査になるのです。大人であれば、そうやって時間をかければ、粒度の細かい、深い意識を語らせることができるはずです。「その場限りの」意識調査は、被験者の本気モードを引き出せていないと考えます。
では、なぜ、多くの研究者がそれをやらないのでしょうか? 研究成果をいち早く発表したいから。効果や影響は、数字という客観的な指標でとるべきだと考えているから。様々な理由があるのでしょうが、認知実験の本来の目的を鑑みれば、片手間であるという批判は免れません。認知実験は、「ひとの生身の声をとっていますか?」と聞かれて、口ごもらないような姿でありたいものです。
参考文献
[1] 中島秀之, 諏訪正樹, 藤井晴行. (2008). 構成的情報学の方法論からみたイノベーション, 情報処理学会論文誌, 49(4),1508-1514.
[2] 諏訪正樹, 堀浩一編著, 伊藤毅志, 松原仁, 阿部明典, 大武美保子, 松尾豊, 藤井晴行, 中島秀之著. (2015). 一人称研究のすすめ—知能研究の新しい潮流, 近代科学社.
[3] 諏訪正樹, 藤井晴行. (2015). 知のデザイン—自分ごととして考えよう, 近代科学社.
(諏訪研新聞 平成27年7月17日付)