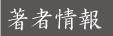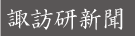AIが生み出す作品
人工知能(AI)が生み出したという作品が世に溢れはじめている。日本経済新聞2019年9月1日の記事(the STYLE/CULTURE)によると、「6月には中国の美術大学の卒業制作展にAIの作品が紛れ込み、観覧者が気づかないほどの出来栄えだったことが話題になった」そうだ。また市場もAIによる作品に価値を見出しはじめていて、高値で落札された事例もあるらしい。
さて、こういった動向をどう捉えたらよいのだろうか? 人の創作じゃないと作品とは認められない! コンピュータによる制作だからといって「認めない」なんて、頭が硬すぎる! 市場は価値を見出しはじめているではないか! 喧々諤々、様々な意見がありそうだ。
3つの問い
私は、以下の3つの問いに分けて論じることが建設的であると考えている。
1. AIシステムはアーティストか?
2. AIシステムを制作(プログラミング)したプログラマーはアーティストか?
3. AIシステムが制作したモノはアート作品か?
第一のポイントは、アーティストかどうかを問うことと、アート作品かどうかを問うことに分けることである。AIシステムの機能や能力を決するのは、それを制作したプログラマーなので、1を問うならば、2も問うてみようというのが第二のポイントである。
アートとは?
そもそもアートとはどういう営みなのか? 上記の問いに答えるには、まずこれを考えなければならない。アーティストの制作行為を分析したチクゼントミハイら[1]は、制作行為の本質は、あれこれと素材に触れ、戯れることを通じて、自分なりの問題意識を醸成したり、人として生きる意味を見出すことにあると論じた。アート学生のその後の人生を追跡するタイプの研究(学問的にはlongitudinal studyと称する)において、学生時代の課題制作で観察された上記の行為の頻繁さと、アーティストとして大成することには相関があると彼らは報告したのだ。
問題意識の醸成は、学ぶという行為の本質である。拙著[2]では、問題意識の醸成を、違和感/感触を捉まえる、疑問を呈する、問題点を挙げる、仮説を立てる、目標を立てる、の5つに分類し、この種の認知行為があるからこそ、主体的に学ぶことができると論じた。アーティストは、制作活動を通して生きる意味を学ぶ人たちなのである。
この思想に立つならば、第1の問いの答えは明白である。AIシステムは身体性を持たず、主体的に動いて自分なりの問題意識を育むことはない。自己もない。プログラミングされた通りにデータを収集し、分析結果を出すだけなので、主体的に「生きて」いるとは言えない。つまり、AIシステムはアーティストではないと、現時点で私は考えている。
AIプログラマーが為していること
第2の問いはどうだろう。AIシステムは世の中の全てのアート作品をデータとして取り込むわけでないし、分析アルゴリズム(例えば、Deep Learningの手法)を自分で編み出したわけでもない。それを設定するのはプログラマーである。設定の詳細は私にはわからないが、推定するに、プログラマーが制御できる部分は以下の3つであろう。(a) 大量の作品データを読み込む際の基準を設けること、(b) 分析アルゴリズムを決めること、(c) AIシステムが出力した作品群の中から出品するものを選ぶことである。
さらに言えば、(a)から(c)を一度だけやって出品作を決めるわけではない。(c)の結果が気に食わなければ、(a)の基準や分析アルゴリズムを何度も修正し、彼(彼女)にとって「良い」作品が生まれてくるまで、試行錯誤を繰り返す((a)~(c)のサイクルを何度も回す)に違いない。そうしている間に、(c)の選定基準も次第に、彼(彼女)の心の中で進化するに違いない。
データ収集基準、分析アルゴリズム、出品作選定基準が、プログラマーが「生きる」上での思想や基準を反映したものであるとするならば、(a)~(c)のサイクルを営むプログラマーはアーティストと言えるだろうか? それについての私の考えは後述する。
アート作品か?
先に、第3の問いに答えよう。制作を通じて、自分なりの問題意識を醸成し、生きる意味を見出すことがアート活動の本質であるという前提に立つならば、鑑賞者にとっては、作品を鑑賞して、自分なりの問題意識を醸成したり、人として生きる意味を見出すことがでアートに触れる意義であろう。制作者の想いを想像したり共感したりすることもあろうが、必ずしも、鑑賞者の問題意識や生きる意味は、制作者のそれと同じである必要はない。
第3の問いに対する私の答えはこうである。「鑑賞者が自分なりの問題意識を醸成したり、生きる意味を見出したりすることを促すモノは、アート作品といってよい」と。たとえ、(アーティストではない)AIシステムが生み出したモノであっても、である。
人工知能研究の黎明期にイライザという自然言語処理プログラムがあった。人が喋った音声を認識するのではなく、テキストベースではあったが、タイプ入力された質問を単語単位に分け、データベース上で関連の深い単語を組み合わせて、簡単な応答をするAIシステムである。私の想像で恐縮だが、例えば「父親がとても厳しいのです」とタイプすると、「親子関係は難しいです」などと答えるわけだ。応答を受けた人は、「ほほう、なかなか深いことを言ってくるね」と、思考を刺激されてしまう。イライザは決して「意味」や「問題意識」を理解しているわけではないのだが、人はとかく「深読み」をするのだ。
AIシステムが出力したモノを、鑑賞者が「深読み」して意味を見出すのであれば、そのモノはアート作品と認識してもよいのかもしれない。
リアルタイムに素材や作品に触れることが重要
さて、第2の問いに戻ろう。私の考えはこうである。(a)~(c)の行為の中に致命的に欠けている要素がある。それは、チゼントミハイの言及で述べた「素材に触れ、戯れる」ことである。AIプログラマーは、データ収集(入口)と出力作品の選定(出口)には直接関与しているが、制作プロセスには、アルゴリズムの選別という形で間接的に関わっているにすぎない。素材や、まさに作りつつある作品に触れて、戯れて、その行為そのものから、違和感、疑問を抱き、高次に言語化された問題意識を醸成し、生きる意味を見出すきっかけを得るということがない。
私たちは、ものごとを考える時にメモしたり、絵や図を描いたりする。デザイナーは新しいアイディアを創造しようとするとき、手書きでラフなスケッチをする。それは、素材に触れ、作りつつある作品に直に触れ、新たな思考を芽生えさせるための原始的な形なのだ。認知科学やデザイン科学の分野で論じられてきた、この側面は、アート活動においても本質中の本質であると、私は思う。
であるとするならば、そのプロセスに関与できないAIプログラマーは、アーティストとしての本質的行為を奪われている。Deep Learningを始めとする昨今のAIの弱点は、システムが答えを出すものの、どうやってその答えにたどり着いたのかがAIプログラマーにも解析できないことだと言われている。こと、アート活動においては、この弱点がAIプログラマーをアーティストと認めることを阻んでいる気がしてならない。
参考文献・URL
[1] Getzels, J.W., Csikszentmihalyi, M. (1976), The Creative Vision: Longitudinal Study of Problem Finding in Art, John Wiley & Sons Inc.
[2] 諏訪正樹、藤井晴行 (2015) 知のデザイン 自分ごととして考えよう, 近代科学社.
(諏訪研新聞 令和2年1月16日付)