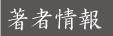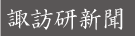体内感覚をことばにする
第4回記事では、からだメタ認知という学びの理論(自分のことばを紡いでからだを変える方法論)を紹介しました。しかし、やってみるとわかるのですが、その道程はなかなか険しく少々の辛苦を伴います。いや、それで当然なのですよ。「これを使えば学習も楽々!」そんな謳い文句があったとしたら、それはまがい物の学びだと思います。昨今は学ぶという行為も商業化され、楽に学べますなどと大安売りする風潮が蔓延っています。“何かを体得したい”と思うなら、学びのプロセスに近道はない、時間がかかって当然なのだと考え、腰を据えて挑む決意が必要です。
さて前置きが長くなりましたが、本稿では、そういう決意をもたれた方に、“からだを考えてことばを紡ぐ”とはどういう行為なのかを紐解きたいと思います。これを読んだからといって、学びのプロセスが簡単になるわけではありませんが、どんなことをどんな風に考えてことばにすることが、からだでの学びを得ることにつながるのかを解説したいと思います。
例えば、ある野球選手が相手投手の速球をものともせず、会心の打撃を披露したとしましょう。いままでそんな打ち方はしたことがなかった、つまり、いまこそ“からだで学ぶ”よい機会であるとしましょう。その体験をどのようにことばに表現し、からだメタ認知を行えばよいのか?それに対する私の回答は、「からだの内部の感覚(以下体内感覚と呼びます)をできるだけことばとして表現することから始めましょう」です。体内感覚とは、専門用語で言えば、自己受容感覚です。身体を動かすことに伴い、筋肉、腱、骨の動きが生み出す内部感覚です。例えば、どっしりと安定している、軸がすっと通っている、左右のバランスがとれている、何か地面と足裏の感覚がしっくりこない、などの感覚はまさに体内感覚の典型です。体内感覚をことばにするのはなかなか難しいのですが、慣れてくると少しずつ表現できるようになります。第4回記事に書いたことですが、ことばにするといっても、他者に伝えるために正しく表現する意図はもたなくてもよいのです。また、自分のことばがからだの内部の実際の状態を再現性高く表現できているのだろうかと心配しない方が得策です。とにかく、体内感覚に眼を向け、拙い表現でもよいからことばで表してみることが肝要です。
内から感じる対象、かつ外から見える対象としての「からだ」
他者は、その選手の身体を客観的に見て、「ああだこうだ」とことばに表現するかもしれません。それも身体を表現することばですが、体内感覚の表現とは全く別物です。こう考えてみると「からだ」とは面白い存在です。本人が内から感じる(専門用語では、内部観測を行うと言います)対象であり、また同時に他者が外から客観的に観察する対象でもあります。その両方を統合したものが「からだ」なのです。客観的な観察対象としての(漢字の)「身体」とは区別して、統合としての「からだ」はひらがなで表記することにします。例を示しましょう。
・A:左足を踏み込んだときに、右肘で身体の軸を左サイドにぬ〜っと押し込むけれど、それが左股関節あたりでぐっと溜まる感覚
・B:右脇が締まったまま右肘が脇腹の近いところを通り、更に踏み込んだ左足のつまさきは踏み込む方向に開かず閉じている
共にからだの状態や感覚を表現することばですが、Aが内からの感じるからだの状態、Bが外から客観的に見える身体の動作・状態です。「からだを考えてことばにしましょう」と言うと、ひとは、ビデオに撮ったり、鏡に映したり、人に見てもらったりして、とかく、Bだけをことばで表現しようとしがちです。内から感じる存在と、外から見える存在を統合したものが「からだ」であるならば、 Aもことばで表現しなければならないというのが、からだメタ認知の理論なのです。
外からの見えを制御するのではない
なぜAもことばにした方がよいのでしょうか?簡単にいえば、からだの内部状態こそ身体行為の基底であり、本人が制御すべき対象だからです。身体の形などの外からの見え(B)は、あくまでも、からだの内部状態の結果として生じる外部状態です。プロの選手のスウィングを形だけ真似てみるアマチュアは多いと思いますが、身体の外からの見えを直接制御しても、何も得られないことが多いのです。“右肘が締まったまま脇腹に近い場所を通る”という外からの見えを制御して達成するのではなく、そういう身体状態を生み出す大元の内部状態を実現することが目的なのです。上記の外部的身体状態が成立しているとき、からだの内部はどのような感覚であるのかを意識することに努め、その感覚を達成すべく内部状態を制御することを目指すべきだと思います。
体内感覚と外からの見えを関係づける
別のことばで言えば、AとBの両方をことばにする行為は、直接の制御対象である内部状態およびその体内感覚と、(結果として生じる)外から見える身体の形を関係づけようとする模索なのでしょう。例えば、左足のつまさきを開かず左足にぐっと踏み込むという身体状態をB1とし、右肘が脇腹から離れないようにバットを振る身体状態をB2としましょう。客観的に外から見える身体の状態としては、部位も別々なので、両者に関係を見出せないかもしれません。しかし、両状態を成り立たせる内部状態の体内感覚が似ていることにふと気づけば、B1とB2は実は深い関係にあること、つまり、両状態は共通の内部状態に立脚する2つの異なる「見え」に過ぎないという理解に辿り着けます。つまり、からだ全体で成立する自己受容感覚Aを介して異なるBの関係性が見えるのです。この種の理解に辿り着くと、外からの見えを制御するよりも、身体の各部位の様々な「見え」を生じさせる大元の内部状態に意識を払う方が得策であると実感できます。からだで学ぶために、なぜ体内感覚をことばにするのがよいのかがお解りいただけたのではないでしょうか。
更新日:平成25年8月8日 諏訪研新聞第5号(平成25年9月発行)より先行掲載